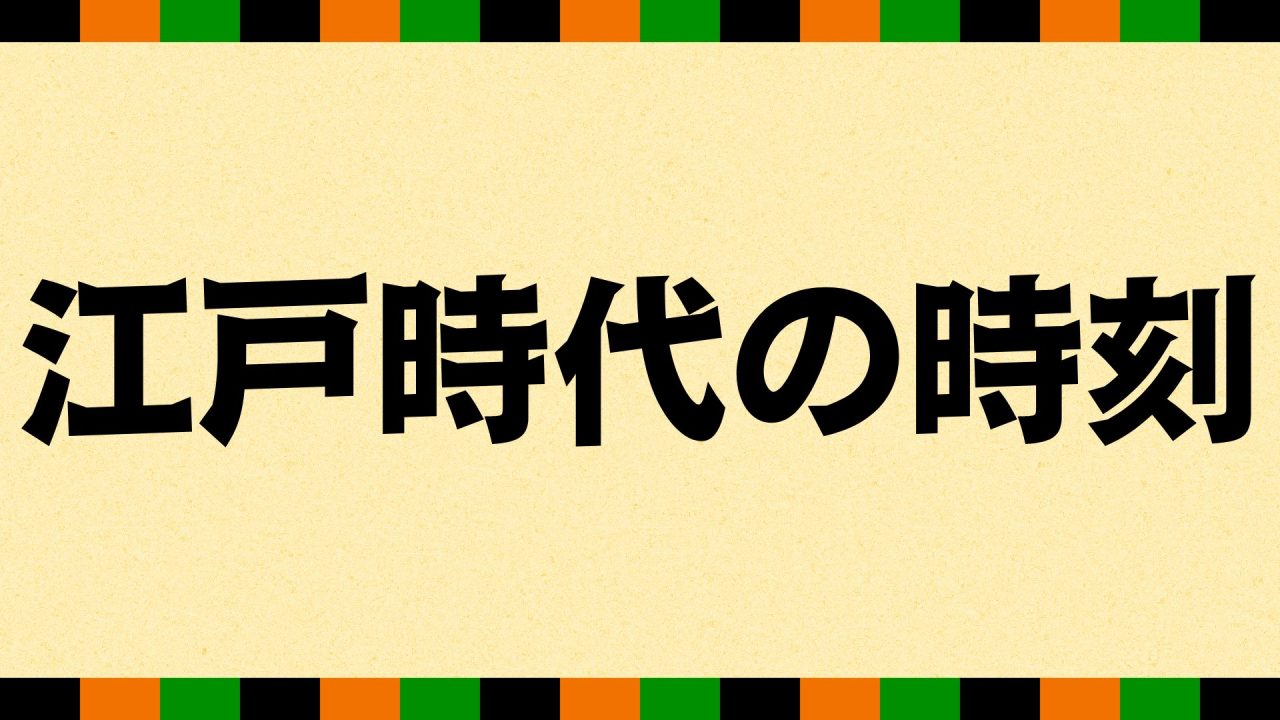本記事では、江戸時代の時刻の表し方と、「何時に何をするか」という生活のサイクルをお伝えします。
江戸時代の時刻の表し方
江戸時代は、一日を「日の出〜日の入り=昼」と「日の入り〜日の出=夜」の2つに分けてから、さらに昼・夜を6分割して「1刻」と数えました。
また、それぞれの時刻には「十二支」も割り当てられています。
その結果、江戸時代の時刻の表し方は、下記のようになっていました。
画像出典:「ゼロから分かる! 図解落語入門」稲田和浩,世界文化社,2018,p.73
江戸時代は、時計がまだ普及していなかったため、庶民は寺などで鳴らされる「時の鐘」を聞いて、時刻を把握していました。
時の鐘では、まず「捨て鐘」を3つ打って、音に気付かせてから、刻の数を打ったため、時刻の最小は「四つ」になっています。
なお、「日の出」の約30分前を「明け六つ」、「日の入り」の約30分前を「暮れ六つ」としていることから、季節によって「1刻」の長さは異なります。
江戸時代の生活サイクル
江戸時代は、「明け六つ(現在の朝6時)」には、商店や銭湯が開きました。
このため、江戸っ子の職人たちは、朝一番に銭湯へ行ってサッパリしてから朝食をとり、「朝五つ(現在の朝8時)」ごろから働き始めます。
昼食の時間は、今と同じ「昼九つ(現在の正午)」ごろ。
そして、「昼八つ(現在の午後2時)」くらいに休憩しつつ、お菓子をつまむことが「おやつ」の語源となりました。
仕事が終わるのは、「夕七つ(現在の午後4時)」で、今よりは少し早めです。
この一冊で「落語の概要」「代表的なネタ」「江戸の文化」「伝説の落語家」のすべてが知れます。
落語に少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ読んでみてください!
なお、本書は「Kindle Unlimited」の読み放題の対象です。
Kindle Unlimitedは、月額980円で本書の価格よりも安いうえ、30日間は無料で体験できます。
とってもお得なサービスですので、よろしければ試しに使ってみてください。