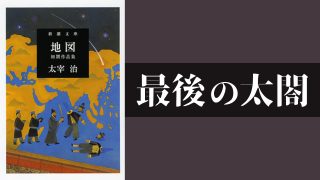太宰が一番最初に書いた作品って、なんてタイトルなの?
現在確認できるなかで、最も古いのは中2のときに、本名「津島修治」の名で発表した『最後の太閤』という作品だな。
『最後の太閤』は、太宰治が世に発表した作品で、現在確認できるなかでは最も古い著作です。
本作は、太宰が青森中学の2年生のときに「校友会誌」で、本名の「津島修治」の署名で発表されました。
本記事では、この『最後の太閤』の全文を掲載したうえで、本作のあらすじや執筆された背景などをお伝えします。
なお、『最後の太閤』は、新潮文庫から出ている『地図―初期作品集―』という著作集に収録されています。
『地図―初期作品集―』には、太宰が中学生や高校生の頃に書いた作品が多数収録されていますので、ご興味のある方は、ぜひ下記から購入して読んでみてください。
書名:地図―初期作品集―
著者:太宰治
出版社:新潮社(新潮文庫刊)
『最後の太閤』の全文
それは太閤の命も已に、あやうく見えた時であった。宏大な伏見城の奥のうす暗い大広間である。広間には諸侯がうようよとうごめいて居る。陰気な暗い重い湿った空気がぐんぐんとささやく彼等の言葉さえなんとなく暗く思われた。裏山の杉の林からジージーージジーーと暑苦しい重たそうな蝉の声が聞こえて来る。
隣部屋に寝て居る太閤は今どんなことを考えて居るだろう。傍らには秀頼も居る。淀方(よどのかた)も居る。しかし北政所(きたのまんどころ)方の居ないのは妙にさびしい。太閤は目を細く開いて秀頼の顔を見上げた。淀方の方に眸をむけた。隣間の諸侯の話声に耳をかたむけた。そして彼は又満足気に目をつぶった。彼の頭には色々な考えが幻の如く、まわり燈籠の如く浮かんで来た。父、彌右ェ門と山に薪をとりに行く彼の姿。父は彼の頬にキッスをした。父と子――飾りけのない貴い姿――あの時と今と――
彼はウットリとなって居た。そして考えは次から次へと進んで行った。
天正十年のことであった。山崎で逆臣光秀を討って主君の仇を報いたときの嬉しさ。彼はたった今でもそれを味わうことが出来た。
つづいて起こった賤ケ嶽の戦。それらは皆眼前に幻となってはっきりと現れた。彼の口元には勝ほこった者のような微笑が浮び出た。
同十二年!! 小牧山の戦!! 彼の微笑がもう顔のどこにも見あたらなくなって居た。どうしても徳川公を亡ぼすことが出来ず和睦を申し込んだ時の彼の心「わしともあろうものが……」と彼は彼自身にも聞きとれそうもない程ひくいひくいひとりごとをもらした。隣間から徳川公の咳がゴホンゴホンとじめじめした空気を伝って彼の耳にとどいた。彼の顔色はだんだん暗くなって行った。
関白―太政大臣、彼の栄達は実に古今に類がなかった。あの当時の彼の勢。彼は今それを思い出したのである。自分でさえ自分自身の勢が恐ろしくてたまらなかった位であった。彼はもうたまらなくなってウーとうなり出した。聚楽第(じゅらくてい)の御幸! 文武百官を率いて諸侯と共に「天皇をうやまい申す」との誓いを立てた時の有様は……おお彼の目は涙でうるんで居る。太閤は心から泣いた。君恩は彼を泣かしめたのだ。四辺の空気は尚一層じめじめして来た。文禄元年の朝鮮征伐が目の先にちらついて来た。彼はどこを見るともなくまた目を開いた。彼の手はかたくかたくにぎられて居た。汗まで手の中にひそんで居た。
彼は急にフーと長い長い歎息をもらした。
慶長元年の明使をおっぱらった時の光景が目の前に浮かび出たのである。
しかし彼はすぐにはれやかな色を顔にただよわした。彼はあのはなやかであった彼の醍醐の花見を思い出したのだ。ほほえみが彼のやせこけた頬にうかんだ。もう彼の頭はボーとして来て何が何やらさっぱりわからなくなってしまった。……秀頼の顔が大きく大きく彼の目の前に幻となって現れた。
そして秀頼はニッコリ笑った。太閤はもうたえられなくなってしまった。そして大声でウハッハッハッハッハッと笑いこけてしまった。
枕もとに侍って居た人々は驚異の目を見はった。隣間の諸侯が急にがやがやとさわぎ始めた。それをおし静めて居るのが前田公であった。
ああ一世代の英雄太閤は遂に没した。
その死顔に微笑を浮かべて……。
華かなりし彼の一生よ。
広間の中からはすすり泣きの声が洩れて来た。
諸侯は誰も面を上げ得なかった。
夕日は血がにじむような毒々しい赤黒い光線を室になげつけた。諸侯の顔も衣服も皆血で洗われてしまったように見える。否彼等の心に迄も血がにじんで居るだろう。裏の林の蝉が又一しきり鳴き始めた。
夕日はかくして次第に西山に沈んで行く……。
太閤はかくしてあの世に沈んで行ったのである。
『最後の太閤』のあらすじ
広大な城の一室で、死期の近い太閤(豊臣秀吉)が床に伏せている。
秀吉は、側にいる息子の秀頼とその母の淀方(よどのかた)のほうへ目を向けてから、隣室にいる諸大名たちの話し声に耳を傾けると、満足したようにまた目を瞑った。
すると、秀吉の頭の中には、さまざまな思い出が蘇る。
父と一緒に、山に登ったこと。
裏切り者の明智光秀を討ち、主君である織田信長の仇を取ったこと。
賤ヶ岳の戦いや、小牧・長久手の戦い。
関白にまで上り詰め、京都に聚楽第(じゅらくてい)という居宅を建てたこと。
民(中国)や朝鮮との争い。
そして、つい最近、京都で催した盛大な花見。
ここで突然、大きな秀頼の顔が、幻となって秀吉の目の前に現れた。
その秀頼の顔がにっこりと笑うと、秀吉は我慢できなくなり、大笑いをしてしまう。
そしてそのまま、秀吉は息を引き取ったのだった。
『最後の太閤』が執筆された背景
『最後の太閤』は、太宰治が青森中学の2年生(数え年で17歳)のときに発表された作品です。
中学時代の太宰は読書好きな青年で、芥川龍之介や菊池寛らの作品をよく読んでいました。
いつしか、「読むこと」だけでは飽き足らなくなった太宰は、ついに自分でも小説を書き始めます。
そうして中学校の「校友会誌」にて、本名の「津島修治」の名で発表したのが本作です。
この『最後の太閤』は、現在確認できるなかでは、太宰が世に発表した最古の作品となっています。
『最後の太閤』の登場人物
- 太閤:豊臣秀吉。
- 淀方(よどのかた):秀吉の側室(一夫多妻制のなかで、「正妻=正室」以外の妻のこと)。
- 秀頼:秀吉と淀方の次男。
- 北政所(きたのまんどころ):秀吉の正室。
- 諸侯:自分の死期が近いことを悟った秀吉が、城に呼び寄せた大名たち。徳川家康もこのなかにいた。
『最後の太閤』における注目ポイント
『最後の太閤』で特徴的なのは、冒頭から硬い雰囲気で話が進んでいくなか、突然、秀吉が息子の顔を思い浮かべて「ウハッハッハッハッハッ」と大爆笑するシーンが挿入されることです。
この「緊張」と「緩和」は、太宰なりのユーモアで、読者の笑いを誘う意図があったと考えられます。
実際、太宰の自伝的小説『人間失格』にも、「学校の作文の授業で、先生を笑わせるような話を書いていた」というシーンが登場します。
また、綴り方には、滑稽噺ばかり書き、先生から注意されても、しかし、自分は、やめませんでした。先生は、実はこっそり自分のその滑稽噺を楽しみにしている事を自分は、知っていたからでした。或る日、自分は、れいに依って、自分が母に連れられて上京の途中の汽車で、おしっこを客車の通路にある痰壺にしてしまった失敗談(しかし、その上京の時に、自分は痰壺と知らずにしたのではありませんでした。子供の無邪気をてらって、わざと、そうしたのでした)を、ことさらに悲しそうな筆致で書いて提出し、先生は、きっと笑うという自信がありましたので、職員室に引き揚げて行く先生のあとを、そっとつけて行きましたら、先生は、教室を出るとすぐ、自分のその綴り方を、他のクラスの者たちの綴り方の中から選び出し、廊下を歩きながら読みはじめて、クスクス笑い、やがて職員室にはいって読み終えたのか、顔を真赤にして大声を挙げて笑い、他の先生に、さっそくそれを読ませているのを見とどけ、自分は、たいへん満足でした。
『人間失格』太宰治
中学生の太宰はその延長で、『最後の太閤』にも読者を笑わせる要素を入れたのだと思われます。
『最後の太閤』で気になる言葉
夕日はかくして次第に西山に沈んで行く……。
太閤はかくしてあの世に沈んで行ったのである。
これは、『最後の太閤』の最後の2文です。
「上手いこと言って、終わらせてやった!」という、太宰のドヤ顔が目に浮かんできます。
『最後の太閤』の考察
『最後の太閤』を発表した2年ほど前に、父を亡くしている太宰。
生前の父と太宰は、あまり親密な関係とは言えませんでした。
本作品で、亡くなる直前に息子の顔を思い浮かべて大爆笑した秀吉を描いたことには、「自分も、それくらい父親に気にかけて欲しかった」という太宰の願望が見え隠れします。
まとめ
本記事では、『最後の太閤』のあらすじや執筆された背景、注目ポイントなどをお伝えしました。
すでに著作権が切れているため、記事中で全文を掲載しましたが、紙で本作を読みたい場合には、新潮文庫の『地図―初期作品集―』に収録されていますので、下記からお買い求めください。
書名:地図―初期作品集―
著者:太宰治
出版社:新潮社(新潮文庫刊)
目次:
最後の太閤
戯曲 虚勢
角力
犠牲
地図
負けぎらいト敗北ト
私のシゴト
針医の圭樹
瘤
将軍
哄笑に至る
口紅
モナコ小景
怪談
掌劇 名君
股をくぐる
彼等と其のいとしき母
此の夫婦
鈴打
哀蚊
花火
虎徹宵話
*
断崖の錯覚
あさましきもの
律子と貞子
赤心
貨幣
*
洋之助の気焔
なお、記事を執筆するにあたっては、以下の書籍を参考にしました。
- 『評伝 太宰治〈上・下〉』相馬正一.津軽書房,1995
- 『新潮日本文学アルバム 19 太宰治』太宰治.新潮社,1983
- 『太宰治の年譜』山内祥史.大修館書店,2012
- 『太宰治大事典』志村有弘・渡部芳紀.勉誠出版,2005
それぞれの書籍の概要については下記の記事にまとめていますので、ご興味のある方は、併せてご覧ください。
太宰治グッズ、販売中!

オリジナルグッズ販売サイト「SUZIRI」で、太宰治の作品をモチーフにしたTシャツやキーホルダーなどを販売しています。
ご興味のある方は、ぜひ下記のボタンからチェックしてみてください!
▼実物はこんな感じです。
『人間失格』モチーフのTシャツとキーホルダーを作ってみました。 pic.twitter.com/KOCYEnwyTK
— コカツヨウヘイ|元司書のライター (@librarian__y) September 5, 2023